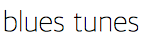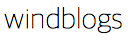| Hotel Rwanda Terry George 2005-02-17 THU. | なんじゃそりゃ?ってタイトルと、Terry George?誰それ?とお思いの方も多いことでしょう。 これ、実は 2004 年にアメリカで製作された「映画」のタイトルで、Terry George はその監督なのでございます。 この BLUES日記では滅多に無い、「白人」の登場ですね。 記憶力の良い方は覚えておられるやもしれませんが、先日の Elmore James 特集(?)の折りに言及いたしました「大虐殺」を、首都 Kigaliにあったベルギー資本のホテルの現地支配人の視野を通して描いた作品、と言ってよろしいかと思います。 ただ、これは昨日付けの A 新聞で採り上げられていたことから、もう一度 Rwanda について目を通しておきたくなったでけであって、現実に、まだその映画そのものは観てはおりません。 アフリカ大陸の内陸にある小国 Rwanda は西は Lac Kivu という湖水を挟んでその両翼では陸路でも Congo と接し、北には Uganda、東が Tanzania、南を Brundi に取り囲まれています。その中央、やや北寄りに位置するのが首都の Kigali で、その 8 時の方向 60km、 Lac Kivuの畔には、1994 年の大虐殺でおよそ 20 万人の Tutsis ─ツチ族が殺された Kibuye があります。 Elmore のところでも書きましたが、この Rwanda における Hutus(フツ族;農耕を生業とし、全土に分布、北部の富裕層を除けば、殆どがいわゆるポヴァーティ・ラインにひっかかるような生活レヴェルを送っていた、とされる)と Tutsis(ツチ族;主に牧畜に従事し、その所有する牛が「富の象徴」とされてきた。したがって、フツ族であっても牛を持つようになれば、「あいつはツチになった」とされ、科学的な意味で分類可能な「民族」の差は無かったとされています。全人口の 15% 弱の Tutsis も国内に分布していましたが、前述の Kibuye だけは濃度が高く、およそ 50 万ほどの住民の半数が Tutsis でした)の間には「族」として識別できるほどのものはその生活形態以外には無く、民族間対立と言うよりはむしろ貧富の差、社会的待遇の差をめぐる階級闘争、とも言えるのですが、そこには独立以前のドイツ及びベルギーの旧宗主国の影が落ちています。 第一次世界大戦で連合国側に敗北するまで、ここを支配していたのはドイツでした。そしてその時期に Tutsis vs. Hutus の最初の種が播かれたと言ってよいのではないでしょうか。 当時の誤った「人類学」から Tutsis をエジプトはナイル流域に由来する「黒いアーリア人(ナチが親交を持った相手国の国民を無理矢理「アーリア人」ってことにしてしまうのも、この流れでしょ)」ってことにして、この地域の支配の手先として重用したために、Hutus からは「恨まれる」存在となっていったようです。 ベルギー領となってからも Tutsis の優勢は変わりませんでしたが、これはドイツが手離した現地の管理システムをそのまま流用しただけで、混乱を避けただけではないでしょうか。 第二次世界大戦の終了後、同地は国連の信託統治となりましたがその間に部族の王が暗殺され、後継の Kigeri 五世はウガンダに逃亡したため、Tutsis の勢力は一層強くなった、とされています。 それが 1962 年の独立後、当初政府首班となった Tutsis の行政に、絶対多数を占める Hutus の不満が次第に高まり、さらには旧宗主国のベルギーも Tutsis との距離をおくようになって来たこともあって、1973 年にはクーデターが起き、政権から Tutsis を追放しました。 こうして政権を手に入れた Hutus は当然 Tutsis を支配下に置き、その勢力を各界から追放していきます。 一方の Tutsis 勢力は雌伏の期間を経てウガンダ国内に本拠を置く Rwandese Patriotic Front : RPF ─ルワンダ愛国戦線を結成し、内戦が開始されました。 政府側ではこれを Hutus をふたたび支配しようとしているもの、として抗戦するとともに Tutsis に対する弾圧も行っています。この段階で南の Brundi や西の Congo に Tutsis が逃亡するのですが、そのことが後にコンゴでは「別な」内戦の火種となります。 1992 年にようやく政府と RPF 間で Arusha Accords と言われる停戦合意が調印され、いったん平穏な時期を迎えるかに見えたのですが、内戦時の Tutsis に対する弾圧や、Hutus による(というよりはその中でも一部の富裕層の支持が篤い)一党独裁の政治自体に国際的な非難が集中するなか、もっとオープンな政治を、と舵を切り直そうとしていた(ま、実は Tutsis 弾圧の張本人であった、ともされていますが)大統領 Juvènal Habyarimana の乗機が「何者かに」撃墜されてしまいます。 またその前後から、ベルギー人ジャーナリストが主導したとされるプロパガンダが「千の丘」放送局から流され続け、それは Tutsis をゴキブリと称し、ひとり残らず殲滅せよ、と呼びかけ続けていました。 こうして 1994 年、大統領の死を契機として Hutus による Tutsis の「虐殺」が始まりました。 そのさなか、首都の Hotel Milles Collines の現地支配人が、逃げ込んでくる Tutsis と、同じく虐殺の対象とされた Hutus の穏健派の人々を構内に匿い、唯一「生きていた」 FAX 回線を使ってアメリカやフランスの政府に連絡し続け、彼らを救った実話から生まれたのがこの映画 Hotel Rwanda なのです。 もちろん、まだ観てもいないんですから、映画としてどうこう、なんてことは書けません。 しかし、そのもととなった事実は、いまだに未解決のまま、我々の前にあります。なぜ国際社会はそれを「放置」したのか? そこには「究極の」黒人に対する「蔑視」があったのではないのか? 白人が絡んでないなら「放っとけばいい」という、西欧の白人中心的な思想がゼッタイ無い、と言えるのでしょうか? ある国連の職員が「何万人のルワンダ人が死のうが関係ないのです。ルワンダ人の命は、アメリカ人やベルギー人、あるいは日本人の命に見合う価値はないのです」と発言した事実をご存知ですか? 前後の経緯がわからないので、それが真意なのか、あるいはアメリカをはじめとする西欧諸国の対応に対する辛辣な皮肉なのかは判りませんが、確かに、ルワンダの悲劇を誰も止めなかったことに対する「悲惨な『解』」ではあるのかもしれません。 映画では、なぜ、この惨劇が起きたのか、は描かれていないらしいのですが、実際、ちょっと首をつっこんだだけでは、とても解きようがない縺れた事件です。ヘタに安直な「見方」を導入してしまったら、むしろ真相からは離脱していってしまったでしょう。 かえって、じゃ一体なにがあったのか?って考え始めるキッカケとなってくれるんじゃないでしょか。 本当のことを言えば、一日のうち、限られた時間で書く、この日記ではとても扱いきれるような対象ではないのでしょうが、ついルワンダと聞くと黙ってらんなくて、ね。 「ぷ」さんがどっかから聞いてきた市内のお餅屋さんってとこに行ってみました。 小じんまりしたお店に入るとショウケースがひとつ。そこにお団子や大福、おはぎに「おいなりさん」が並んでいました。うひゃひゃ、こりゃもう「おいなりさん」買うっきゃないでしょ! 「ぷ」さんはゴマあんのダンゴね。 おいなりさん、紅ショウガでピンクになったご飯が「かなりな」密度で詰まってるせいか見かけよりズッシリ(はオーヴァーだけど)してます。お味はかなり甘め。やはりお餅屋さんで作ってるだけのことはあります(?)。でも嫌いじゃないぞ。 沖野の餅屋(いつもの黒石のお店ね)のよりちょっと小ぶりで少し甘い、と。 あ、「ぷ」さんの買ったゴマ団子、いっこヌスんだ(?)けど美味しかったですよ。頼むと、目の前でたっぷりのゴマあんの中に団子をくぐらせてくれます。うん、なかなか楽しい演出ですねえ。 |
permalink
No.1031