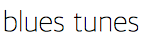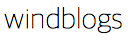| About the Maxwell Street Living Meltin' Pod 06-01-28 SAT. | Johnny Williams の Worried Man Blues に関連して、なにげなく、Maxwell Street 関係で検索をしておりましたら、第二次世界大戦中のアメリカ・レコード業界と Maxwell Street についてのハナシが出て来て、例のストライキの件がちょっとだけ「判った」よな気がいたします。 で、本題の Worried Man Blues はまた日を改めて、ということで(ホントか?)。 W.W.II 開戦当初のアメリカのレコード業界において、Bluebird が Chicago ではもっともメジャーなレース・レーベルだったのですが、戦時物資統制によってレコード盤の原材料であるシェラックが配給制になると、やはり、と言うか、当然のようにブルースなどの「黒人の音楽」が真っ先に減産の対象となります。 さらに the American Federation of Musicians( AFM:「アメリカ音楽家連盟」でしょか)のトップ J.C. Petrillo ─ James Caesar Petrillo: born Mar. 16, 1892 - died Oct.23, 1984、Chicago 生まれ。トランペットを吹いていたようですが演奏家としての資質にはさほど恵まれてはいなかったようです。しかし、政治力というか統率力という側面ではかなりのものだったようで、1919 年にスタートした the American Federation of Musicians に演奏家たちを参加させる活動を熱心に進め、そんな彼の資質はやがて 1922 年に地区委員長のポストに彼を押し上げ、さらに 1940 年にはついに AFM 全体のトップに君臨するようになっています。1958 年までの 18 年間そのポストにあって政治力を発揮しました。1960 年代には公民権活動にも関わっています。 ─ が、当時、台頭し始めていたジューク・ボックス産業に対し、演奏家たちの権利を侵害するものだ、としてロイヤリティの支払いを求める闘争を開始し、それが決裂するや、1942 年から、「全組合員の一切の新規録音をボイコットする」作戦を開始しました。 これによって多くのスタジオが閉鎖されたと言います。 そしてそのユニオンの闘争は「ストリート・ミュージシャン」たちの演奏活動にも影響を与えたみたいですねえ。 ユニオンでは加盟組合員の街頭での演奏までを規制しようとして、それが原因でユニオンを離れたミュージシャンもいた、と言われています。 なにしろ、街頭はもちろん、一切のライヴ活動までも制限しようとしたらしく、それでは「生活」そのものが危うくなる「日銭ミュージシャン」にとっては死活問題なワケですから。 Blues Unlimited のインタビューに答えて Johnny Williams ─ barrel house 04 Chicago Boogie では、Johnny Young とともに Money Talking Mama を演奏し、さらに自身のヴォーカルでも前述の Worried Man Blues を録音しています。 Johnny Young とは「 Cousin 」となっていますが、例によって、それがコトバどおり「いとこ」であるかどうかがちと「?」。ま、それとは別にカンケー無いと思いますが、"Uncle" Johnny Williams と呼ばれていたようです ─ は、「ユニオンに加盟してたら、気楽に Maxwell Street に出かけて、そこにいた誰かと一緒に演奏する、なんてことは出来ないんだよ。」と発言しています。 この時期の Chicago にあっては、そのような政治的(?)バイアスが街頭のミュージシャンに対しても「かかっていた」のでしょうね。 確実なのは、この時期を通じて、それまでのメジャーであった Bluebird などに対抗し得る「独立系」のレーベルが次第にそのポテンシャルを増大させていた、と言うことでしょう。 いったんレコード会社の「くびき」を放れたミュージシャンたちは、「押し着せ」ではない、自分たちのサウンドを尊重して録音させてくれる、レコード会社というよりは「録音屋(?)」とでもいうような小さな業者のもとでもレコードは作れることに気付き、なかにはそんな録音でそれなりのヒットがあれば「会社化」していくものも現れるようになります。 1944 年にようやく AFM のストライキが終結し、すべての新録音が解禁されたときには、Bluebird はすぐに「お馴染み」のミュージシャンを集めてレコード製作を開始しました。 ただ、戦前と異なっているのは、この僅かな期間を経て、市場のニーズは変化し、さらに多様化したソースを受け容れる素地が形成されていた、と言う点ではないでしょうか。 そこに戦前のままのサウンドの「再現(あるいは延長線上?)」から始めようとした Bluebird に対し、次第に頭角を現してきた新興のレーベルが侵食を開始します。 シェラックの配給制も終り、さらに戦後の高揚した消費動向もあって数々の小レーベルが乱立し、そのような状況のなか、19 世紀に、東欧からのユダヤ移民によってその居住者の多くが占められて Jew Town と言われ、20 世紀に入ってからは、裕福になった彼らが「それぞれに」移転して行った後に替わって住むようになった黒人たちがいつしかメイン( 1910 年あたりにはすでにその人口の 60% を黒人たちが占めていた、とされます)となっていた Maxwell Street には、有名・無名を問わず、数々のブルース・プレイヤーたちが「たむろ」し、そこはまさに Maxwell Street School として、Little Walter のようなビッグ・スターも輩出するワケですが、彼のような「有名人」は、その生涯について資料も残ってはいるのですが、それ以外の、例えば Othum Brown にしろ、先日の Boll Weavil にしろ、そのデータは到底「充実している」とは言い難く、そのひととなりさえよく判らない、というのがザラです。 また、例の Robert Night Hawk の Maxwell Street でのライヴでも言及しましたが、新たに流れつくミュージシャンや、逆にいつのまにか「見なくなったねえ」なんてミュージシャンも多かったようで、実際に音源として残っていても、どこの誰なのかさっぱり判らない、なんてケースもあるワケです。 あるいは、そのような「定着しない」プレイヤーが多く出入りしたことによって、それまでの Bluebird サウンドのような、ある意味「完成し定着していた」枠が外され、より「生(なま)」な荒々しいブルースが Chicago に持ち込まれた、と捉えることも出来ますが、一方では、いわゆる「プロデューサー」的な存在を介在させずに、その Bluebird で確立されていたような「公式(こんな曲構成で、タイトルはこんなふう、楽器の編成は⋯みたいな「ノウハウ」ね)」をまったく知らないまま、自分のスタイルをそのまま貫くことで、都会的にまとまって「ある意味、完成されてた」それまでの「コンシューマーズ・ブルース」を、もういちど「プレイヤーズ・ブルース」に揺り戻した、ということも出来るのかも? barrel house bh-04 Chicago Boogie に収録された ORA NELLE の楽曲を聴くと(もちろん Boll Weavil などのサウンドは、ちょっとあてはまらない、とは思いますが)、まさに街頭でのパフォーマンスに必要とされる「いかに客を惹きつけるか」というところに「特化」した(あ、本人たちは、別にそんな意識はなかったのかもしれませんが)スタイルが、後のバンド化への「後から思えば」の重要なマイルストーンであったのかもしれません。 その Maxwell Streetで他のプレイヤーの演奏に触れ、あるいは自分の演奏を「あ、アイツが聴いてる」と意識することで「音」も当然のことながら変わっていくワケですから、教えよう or 教わろう、なんて思わなくとも、そこはリッパに(?)Maxwell Street School であった、と言うことができそうです。(つづく⋯ ような気がする⋯?) |
permalink
No.1377