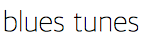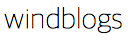| Hoochie Coochie Man Magic Sam 06-02-09 THU. | 意外と軽いテイストの Hoochie Coochie Man と感じられる方もおられるかと思いますが、ワタシとしちゃあ、このくらいあっさりと、「おどろおどろしくない」演りかたのほーが好感が持てますねえ。 Shakey Jake のひらひらと舞うようなハープをかいくぐって忍び寄ってくるような、こんなスタンスの仕上げもなかなかに魅力があります。 このアルバム、Delmark DS-651 : the MAGIC SAM Legacy(またまたアナログディスクでございますが)のジャケットではチェリー・レッドの Epiphone Riviera(ただしネック・ヘッドのトラス・ロッド・カヴァーはブラック)を構えた Magic Sam の画像が使われておりますが、珍しくもそのポジ・フィルムの全幅までが使われており、使用されておるのが 220 Kodak Echtachrome、そして左サイドやや上からの強烈な閃光で撮影されておることを勘案すれば、ヒョっとしてカメラは二眼のローライフレックスではなかったか?などと推理してみるのも楽しいのですが、もちろん、ここにおいでになるみなさまにとっちゃ、そんなこたどーでもいいことでございましょう。 ま、やかましい!と言われるのを覚悟で付け加えさせていただきますってえと、裏面のモノクローム写真のほーは 135(つまり一般的な 35mm フィルムですね)の Kodak Tri-X っちゅう高感度フィルムが使用され、もちろんフラッシュなど使わずに「場明かり」で撮影されております。 その上さらにさらに蛇足を言えば、表裏ではおそらく撮影者も撮影日時が異なっておるのではないでしょうか。表では黒いタートルの上にラメ入りの変わったトップスを着込んでおりますが、裏のほうでは、首のとこだけ見ると同じよな黒に見えますが、リブが粗く、なによりも首から下では大きな横縞が見えてますから「明らかに」違うタートルの上に、ハーフ・プラケットまわりと袖口にエスニックっぽい刺繍が施されたアフリカン・テイストの感じられる衣装を着ております。 Ann Arbor のステージでも、また Black Magic のジャケット(スタジオではなく、どっかのクラブでの演奏シーン?)でもそうでしたが、ともかくタートル・ネックが好きみたいですねえ。 ヨーロッパでのスーツ姿、それに Ann Arbor Live のアルバム・ジャケット中側のステージ写真でのスーツ姿を別にすれば、たいてータートル・ネックを着てるよな気がいたします。 ま、それが彼の音楽にどー関係すんだ?と言われればちと困るんですけどね。 1967-10-18、Chicago の Stu Black Studio での録音でバックはおなじみ Mighty Joe Young にShakey Jake、ベースが Mack Thompson、ドラムは Odie Payne。 あ、この機会に Odie Payne についてすこし⋯ Odie Payne が生まれたのは 1926 年 8 月27日の Chicago でした。 子供のころから音楽に興味を持ち、手に入るものならばクラシックだろうがミュージカルだろうが、なんでも聴いていたようで、10代ともなると、ドラマーの実際のプレイを見るために、よくクラブにも忍び込んでいたそうです。 高校では音楽を学び、その後すぐ陸軍に入りました。 除隊してからは Roy C. Knapp のパーカッション・スクールに入り、ドラムを本格的にマスターしています。 1949 年、ピアニストの Little Johnny Jones と演奏していたところを Tampa Red に認められ、彼のバック・バンドに参加することとなりました。 1952 年の11月には Chicago の Universal Studio で Joe Bihari による Elmore James のレコーディングに参加。 ここではすでに「あの」メンツが揃ってますねえ。つまり J. T. Brown のサックス、Johnny Jones のピアノ、Ransom Knowling のベースに Odie Payne のドラムからなる元祖・純正・本家(?)the Broomdusters でございます。 この有名なグループは、名前こそ同じでも、実態はかなりのヴァリエーションがあるのですが、この Odie Payne はその中でももっとも Elmore James との付き合いが多く、その関わったトラックは 30 を超えます。 当然、彼の存在はシカゴのブルース・シーンにあってかなり重要なものとなり、Elmore James 以外にも 1950 年代後半には Otis Rush や Magic Sam、さらには Buddy Guy などのバックに参加しました。 そして Chuck Berry、Sonny Boy Williamson II、Muddy Waters、Jimmy Rogers、Eddie Taylor(特に 1977 年には Louis & Dave Myers とともに Eddie Taylor のバックとして来日し、ここ弘前市にまで訪れております)と言ったシカゴの一時代を築いたブルースマンのリズムを支え、それ以降のシカゴのバンド・スタイルにおけるドラムの位置づけを確定した、とも言えるでしょう。 基本的には Peck Curtis などのルーラルなリズムとは異なり、あくまでも都会的な、ルーツをジャズ系の「軽い」ドラミングにおいたような「華やかさ」もあって、事実、ジャズのコンボとの録音も存在するハズです。 音的にはかなりハイ・スピードのキックがよく云々されますが、一般的な印象としては「うわもの」— スネア(のロール)やライド・シンバルの効果的な使用など、軽い音域に味があったように思います。 実際に 1977 年に目の前で見た Odie Payne は、あまり気難しいところが無さそうな気さくなオッサン、という印象でしたが、シカゴでも彼は多くのひとから愛され、それもあって数々のレコーディングに顔を出した、という部分もあったのかもしれません。 1989 年 3 月 1 日、Chicago で死亡しました。 |
permalink
No.1389