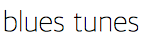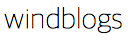| Next generation Alligator Tales vol.54 06-12-07 THU. | AL-4821、Michael Hill's Blues Mob の Bloodlines。 え~と⋯これも from New York です。 でも、これはまた別な意味で変わってるんですよね。 オフ・センターで「辺縁系」なポジションからブルースを照らす不思議な色光、てな感じでしょか。 あの Sly and the Family Stone がブラック本流(?)よりもむしろ白人のロック層に支持されたのとも微妙に違うのですが、なんだか、それまでロックばっかし聴いてきたひとたちにもアピールする「ブルースみたいな音楽」とでも言うか、ネはロックやフュージョンあたりをバリバリやってたミュージシャンがブルースやると⋯みたいなスタンスを感じますねえ。 まずこの Michael Hill ですが、生まれが 1952 年、ニューヨークの「サウス・ブロンクス」! そっからして今までにないタイプ、と言えるかもしれませんねえ。 でも、別にブルースマンはミシシッピー川に沿った南部の諸都市あるいはその周辺、デルタ地帯の農園、でなきゃシカゴのサウスサイドで生まれてなきゃいかん!なんて法律は無いワケで、別にメンフィスで人を殺してなくても、はたまたフィジーで生まれてようが、セイシェル諸島で生まれてようが、アメリカの現実のなかで、黒人として「生きて」きていたら「ブルースマンにはなれる」のでございます。 ただ、このひとの場合、ブルースばかりではなく、フュージョンやレゲエ、ファンクに R&B、そして、むしろロック・ミュージシャンとしての側面が強く、そこらに「異端の匂い」を嗅ぎつけて火あぶりにしちゃおうとするファンダメンタリストもいるでしょね。 そもそも彼がギターを「弾き始めた」のが 1970 年だそうですから、言わば、この Alligator Records が産声を挙げる「前夜」てなもんでございましょう。そしてその彼が最初に遭遇した(あ、これは修辞的表現でして、もちろん、もっとちゃうギターは聴いてたハズですが、彼のココロに「最初に突き刺さった」てな意味でございます)のが、やはり!の Jimi Hendrix! ほらほら、そう聞いただけで異端審問官が色めき立っていますねえ。 なにはともあれ、この Jimi Hendrix との邂逅が彼にギターを弾く「強い」衝動を与えたもののようです。そしてそこから Albert King、B.B. に Albert Collins へと発展し、さらに Bob Marley を知り、Curtis Mayfield にたどりつくことにより、もっと社会性を持った曲を作りたい、という姿勢を形成してゆく⋯ 1970 年代の彼は、レコーディング・セッションのサイドマンを続けながら、日中はタクシーの運転手として生計を立てていたようです。 その時期、リヴィング・カラーを結成する前のヴァーノン・リードが在籍した Dadahdoodahda というニューヨークのバンドに加わり、その交流がこのアルバムへのリードの客演となっているのでしょう。 彼は、その所属していた Black Rock Coalition(この Black Rock Coalition は、音楽産業全体の黒人ミュージシャンに対する不当な位置づけに対抗する目的でギタリストのヴァーノン・リード、ジャーナリストのグレッグ・テートおよびプロデューサーのコンダ・メーソンによって 1985 年に設立された。アーティスト、プロデューサー、A&R、さらに音楽ファンの一部も取り込んだ B.R.C. は、黒人アーティストたちの完全に自由な創造活動を支えるアメリカ国内随一の非営利団体となっている) を通じてジャズやファンク、そしてブルースにも親しみ、Shanachie Records の Tribute to Curtis Mayfield にも参加しています。 そして 1994 年、それらの豊富な「言語」を駆使して彼なりの世界を構築するかのようなこのアルバム Bloodlines が完成します。 もしかして、基本となるフォーマットはシンプルなものが良い(と思ったのかどうかは「?」ですが)からでしょうか、社会の抱える様々な矛盾を歌う際に、彼がそのフォームとして選んだのがブルースを基本としたこのスタイルだった、ということなのかもしれません。 このアルバムは Living Blues の選定する the Best Debut Album of the Year を獲得しています。 それを構成する楽曲は、厳密な意味でのブルース・フォームからは外れる場合でも、その底流にはやはりブルースの「時間」が(ってのもヘンな表現ですが)流れているような気が⋯ ただし、そこで歌われているのは、やはり前述の Curtis Mayfield あたりにも通じる、もっとソーシャルなテーマであり、たとえば一曲目の Can't Recall A Time。その最後のほうに出てくる Most get less and less while just a few get more and more (多くのひとびとがますます「失っている」ときに、ごく少数のひとはさらに多くのものを「得ている」) という一節。 その社会的不公平の全体を俯瞰する視点はむしろ Sly を思い出させます。 で、モノは音楽である以上、そこでどんなことが歌われていようと、「音」としてシンパシィが得られなければ、存在する意味は(歴史的には「ある」かもしれないけど)無いですよね。 その音ですが⋯ まあ、ワタクシがしょっちゅうなにかと言うと持ち出して「バカの代名詞」みたく使ってる「 1950 年代および 1960 年代のシカゴ・ブルースだけを金科玉条のごとくあがめたてまつり、それ以降のブルースを堕落したものと捉えておる、いわゆるシカゴ・ブルース・ファンダメンタリスト(ま、いっそシカゴ・ブルース・シンドローム、でもいいかも)」のみなさまには、まずクソミソに言われそな音でございます。 例えばこのギター。まさにロックそのもののテクスチュアと自由奔放なフレージング(でもちゃんとカウンターとってるけどね)。 そのトーンもさることながら、インプロヴィゼーション一歩手前みたいな動きまわるベース。 ボトムに色を添えるデジタル・ライクにコンティニアスなキックが快いドラム。 さらに単なる「ファンキー」というのとは一味ちがうキーボード⋯ う~ん、どれをとっても、むしろそれまでロックを聴いていたひとたちとの親和性が目立ちますよね。例えばリヴィング・カラーのヴァーノン・リードみたいな⋯と思ったら、前述のごとく、本人が Soldier's Blue に登場してギター弾いてるじゃないの! とまあ、ことほどさように、「ロックやフュージョンの言語を多用したブルース」的なスタンスが強いアルバムです。 これによってブルースに興味を持ち始める若い層がいるかもしれません。いや、いるといいなあ。 とあるところで、EC あたりのブルースを「黒人のブルースへの真摯な敬意に溢れている」なんて書いてあるのを見て「ぐぇっ!」となりました。 ワタシに言わせりゃ「ムシのいい誤解に溢れている」ってことになるんですけどね。 おそらくあのへんを聴いて、自分もブルースやろう!なんて思うのは非黒人ばっか、って気がいたします。 そこいくと、この Michael Hill の音は、(ラップやら Hip Hop 全盛の現代では)少ないかもしれないけど、「黒人の」次の世代になにかを手渡していけるよな気がするぞ。 それがファンダメンタリストどもからはどんなふうに呼ばれることになろうとも、ね⋯ さて、Mob ってのは、普通あまり日本人の日常会話には出てきませんよね。 群衆やら烏合の衆、暴徒、なんて意味もあるようですが、でも、日本でもこの単語が割とふつーに使われてる業界のひとつに「マンガ」の世界があります。 センセは主人公や主要な大道具・小道具を描くんですが、その背景の「その他大勢」=モブ、はアシスタントなんてゆうひとの担当だったりします。 また、ときには遊びにきた同業者の、別なセンセが「遊びで」背景の群衆を描いてったり(すると「モブはXX先生が描いてくれました!」なんてクレジットが入る)。 まあ、なんの業界でも、そこ特有の単語が意外と定着してたりするんでしょね。  今日のオヤツは Dotour のモンブランです。 やや小ぶり。甘さはそこそこ「来ます」。 この半球形じゃなく円錐系になりますが、似たようなテクスチュアなのが宮野のモンブランですね。 これでは「てっぺん」にマロン・グラッセがちょこんと載っかってますが、宮野のは中に渋皮煮が潜んでいるんですよ! ⋯あ、話はいいから画像はどうした!ってことですよね? でへへ、つい撮影すんの忘れて食べちゃうんですよ。ま、そんだけ美味しいってことでして。 よ〜し、次こそは宮野のモンブラン、画像アップしよ! っていつになるか判らないけど⋯ |
permalink
No.1690