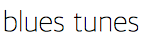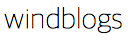| Women Be Wise Sippie Wallace 03-08-27 | 昨日の Lucille Spann に続き(あっ!言うの忘れてたけど、「BLUES 日記」初の女性アーティストの登場だったんだ!)今日も Blues Lady の登場です。おまけにこちらも同じ 1972 Ann Arbor Blues And Jazz Festival での演奏でございます。 実は他にも 1966 American Folk Blues Festival での Suitcase Blues も候補には挙がったんですが、やはり聴き比べてみると、こちらのほーが「いい」! あ、でも、「うんにゃ!ワシゃあ Suitcase Blues じゃ!」ってお方もおられるやもしれませんねえ。 Suitcase Blues、ワタシにはあの Little Brother Montgomery のピアノがちょっと ウルさかったんでげす。なんかヴォーカルを活かす、ってえピアノじゃないよな気がいたしまして。 なんでかマイヤースとしか書いてないけど、たぶん(?)Dave Myers のベース(ウッドだと思うけど、これも「たぶん」ね)、そしてドラム、Freddie Below というバックで・・・なんかモンダイ無さそなんだけど、うー、聴いたらあましよくない・・・Ann Arbor にしよか? てなワケで昨日と同じアルバムからのセレクトになってしまいました(決して手抜きではございません!って誰も信じないよなあ、フダンのワシを知ってるから)。 いかにも、なボニーレイットのギターに導かれて歌い出す、クラシックなスタイルのブルース。 ありし日の(って、実際その時代を知ってるワケじゃないんで憶測でモノを言うな、って言われそだけど)、ジャズとブルースが明らかに溶けあっていた Blues Ladies の時代を思わせるこのテクスチュアは(おそらく)彼女に心酔してるらしいボニー・レイットが大いに寄与しているものと思われます。 ベースの Freebo や、途中ソロをとるクラリネット(それともソプラノ・サックスか?)の John Payne、ピアノの Lou Terricciano、そしてドラムの Chris Parker というバック・ミュージシャンは、Bonnie Raytt 自身のアルバム、名作と言われる Give It Up に収録されたオープニング・ナンバー Give It Up or Let Me Go のメンバーそのもの・・・ とは言っても、その時のメンバーがそっくり「そのまま」ってワケじゃあなく、ナショナル・スティール・ギターでサイドを切っていた Jack Viertel、ウッド・ベースを弾いてた Dave Holland、コルネットの Peter Eckland、そして「トロンボーン」をお吹きになっておられた我らが Amos Garrett センセはここにはおいでじゃあございませんでした。 え?Freebo がベースじゃなかったのか、って? 彼はねえ、ベースを Dave Holland に任せて「チューバ」吹いとりましたんですよ。 先日の Eddie Taylor のUK録音もそうですが、ヘタに張り合っちゃう「対等だ、と思い上がってる」共演者より、その中心となるブルースマン、あるいはブルース・レデイに「心酔」してる非黒人のミュージシャンがバックをつけたほうが、「引き立つ」とゆうケースがケッコーあるよに思いますが、ここでの Sippie Wallace もそうじゃないでしょか? 時々音程がさまよい出ちゃったりするけど、このナチュラルさは昨日の Lucille Spannとは対照的です。なかば唸るような低く抑えたヴォーカルはしかし、決してパワレスなんかじゃなく、まるで百戦練磨、海千山千のバアチャンが、ケツの浮き立ってる娘っ子をさとすよーに、はたまた言い聞かせてるが如く なあ、よーくお聞き、オンナは賢くなんなきゃいけないよ。まず口を閉じとくことだね。 で、自分のオトコのことを言いふらさないことだ。 ベッタリ座りこんで、世間話にうつつを抜かして、自分のオトコのいいとこなんてノロケてちゃあいけないよ。 ほら、みんな、その大事なオトコを狙ってるんだからねえ。 陰じゃあみんな嘲笑ってるんだよ。自分のオトコをジマンなんてするんじゃないよ。 ・・・ いかがですか?これが的を射たアドヴァイスなのかどうかは「女性でなければ判らない」のかもしれませんですねえ。でも、なんだかワタクシ、この歌詞が気に入ってるんですよ。とっても日常的で、ライフ・サイズそのままの親密さ。 1898 年 11月 11日に生まれた Beulah "Sippie" Thomas は Texas 州 Houston で育ち、バプティスト教会の宣教師だった父のもと、教会でピアノを弾いたり歌ったりしていたようです。 ただ、まだ小さいころから夜になると家から忍び出して、地方のヴォードヴィル・ショーや、テント・ショーに通っていたみたい。 10代の前半で彼女と兄の George、弟の Hersal は Texas 州各地を廻るテント・ショーに加わって演奏を始めています。 1915年には New Orleans に移り、兄の George と一緒に暮らしていましたが(ただし、これを Hersal と一緒に New Orleans に出た、とする資料もあり、多少の混乱が見られます)、1917年には Matt Wallace と結婚。 その New Orleans にいる間、彼女は兄の友人だった King Oliver や Louis Armstrong のようなジャズ・ミュージシャンと出合っています。 1920年代の初頭には彼女を「 The Texas Nightingale 」と謳ってツアーを組んでいた the TOBA vaudeville circuit に参加し、1923年には先に Chicago に出た兄弟を追って北上し(ただし兄弟と一緒に Chicago に行った、としている資料もあります)、Chicago ではカフェやキャバレーで演奏を開始しました。同年末、彼女は OKEH Records と契約し、Shorty George と Up the Country Blues の二曲を吹き込み、そのヒットによって彼女はいちやくスターとなります。OKEH にはそれ以降1929年まで、40曲ほどを録音しています。 このアナログ・ディスクに付いてきた日本盤のライナーの中で、中村とうよう氏は Women be Wise を1929年の作品、と紹介していますが、どうも Discography では発見出来ず、でございました。 1926年には彼女の弟の Hersal がわずか 16才で食中毒(?)で死亡していますが、しばしば兄弟が音楽を供給することもあるものの、ほとんど彼女自身で多くの曲を書いていた、という点で古典的ブルース歌手にしてはユニークな存在だったと言えるでしょう。 サイドマンには New Orleans の最良のミュージシャンとも言うべき King Oliver や Louis Armstrong、 Eddie Heywood、Clarence Williams に Sidney Bechet、そして Johnny Dodds などなど、が揃っています。 1929年には彼女は Detroit に移り、1930年代の始め、ショウ・ビジネスから身を引いていますが、その理由として、音楽ビジネスの周辺にイヤ気がさした、とするもの、一方ラジオの普及によるレース・レコード・ビジネスの退潮によるとする資料などが存在し、ちょっと判断に迷うところです。 しかし、1935年と1936年、彼女の叔母の Lillie、彼女の夫の Matt、そして兄の George までが(彼だけは路面電車に轢かれた交通事故によるものでしたが)相次いで死んでしまいます。 この不幸によってもたらされた「ココロの空白」を埋めるため、彼女はデトロイトの the Leland Baptist Church のオルガン奏者およびシンガーとして、ブルース・シーンからは身を退いてしまったのです。 その「お務め」は以後 40年も続くのでした。 そして1945年の 9月に一日だけ Mercury Records のためにレコーディングをした以外、1966年のカムバックまで、ブルース・シーンに浮上してくることは無かったのです。 その彼女のカムバックは Victoria Spivey によるとこらが大きいでしょう。 1965年に、一部のファンによって彼女の再評価が始まり、しかも本人が現在も生存しており、かつ教会で、とは言え「現役の」ミュージシャンであることが判明し、Sippie Wallace のカムバックを期待する声が高まってきたのを受け、ふたたび「悪魔の音楽」の世界に戻ってきたのですが、それを助けたのが友人の Victoria Spivey でした。 一緒にフォーク・ブルース・フェスティヴァルに出演し、ふたりで組んだアルバム Sippie Wallace and Victoria Spivey を、次いで彼女のソロ Sippie Wallace Sings the Blues( 1966 Storyville label )をリリースしています。 また、ディスコグラフィーによれば、Alligator Records から1992年にリリースされた Women Be Wise ALL4810 も Roosevelt Sykes と Little Brother Montgomery を伴奏者として、1966年に録音されています。 また、その翌年には the Jim Kweskin Jug Band と Otis Spann と一緒にスタジオ入りし録音をしたのですが、この時のテープは実に1990年代の初頭に Drive Archive label から Mighty Tight Woman として発売されるまで陽の目を見なかったのです。 1970年には発作を起こし、以来、車椅子での生活となりますが(つーことは Ann Arbor でもそうだったんですね)1980年代に入るとライヴやレコーディングを再開しています。 1982年にはボニー・レイットの仲介で Atlantic Records と契約、そのボニー・レイットも参加したそのアルバムは1983年に発売され、W.C. Handy Award の年間ベスト・ブルース・アルバム賞を獲得、またグラミー賞のトラディショナル・ブルース部門のノミネート作品ともなりました。 1983年と1984年にはドイツのブーギ・ウーギ・ピアニスト Axel Zwingenberger とツアーし、レコーディングも行っています。 彼女のラスト・コンサートは1986年5月のドイツの Mainz でのライヴでした。そして同年11月、彼女の88才(つまり「米寿」ですね)の誕生日に世を去りました・・・ って、ん?この資料じゃあ 11月11日じゃなく、11月1日になってるぞう?およよ、誕生日に「異説」登場! Women Be Wise は Atlantic( Warner-Pioneer ) P-5090〜1A ann arbor BLUES & JAZZ festival 1972 に収録されていますが、他に Alligator ALL4810 Women Be Wise、Atlantic の Sippie. With Bonnie Raitt などにも収録されています。 |
permalink
No.493