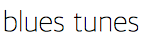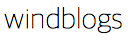| The Thrill Is Gone Little Milton 03-09-04 | 先日の Sugarcane Harris の Stretchin’ out に続き、またまた、本篇(?)の "Favorite Songs" でも採り上げてる曲の登場でございます。 収録されてるアルバムは Stax の "Waiting For" Stax-Victor VIP-5036(アナログ盤)。 Little Milton と言えば 1968年の Grits Ain't Groceries っちゅーのがブルース界のジョーシキなのやもしれませんが、でも、わたくし、フル・オーケステレーションでネッチョリと「大甘」のこれがやたら気に入っちゃってるんですよ。 この曲ばかりか Hey, Little Blue Bird なんて(どー見てもブルースにゃあ思えんけど)コッテコテのバラッドのセンチメンタリズムが、タマに聴くと、カラダに悪いと判ってても時々喰いたくなるクリームがドたっぷりなチョコレート・パフェみたいに「美味しい」んですねえ、これが。 で、そのテイストを残しつつもブルースに色目を使った(あ、これはワタクシが、オモシロがって言ってるだけで、真相は判りまへんで)、ってえのが同アルバム中では、この The Thrill Is Gone じゃあないか?と。 いわゆるマイナー・ブルースって、さすがにネがマイナーなだけあって、やろうと思えばもうトコトン、ダウン指向に出来るんですが、このアレンジも、ニーナ・シモンの I Put A Spell On You に負けず劣らず、「どやっ?どマイナーやで!」てなイキオイで、メローでウェットな、しかしブライトフルな Memphis Horns に、シルキー・スムースな Memphis Symphony Orchestra によるストリングスを配し、実に「思わせぶり」なのねん。 アレンジは Little Milton 自身と James Mitchell(自ら Memphis Horns の一員としてサックスを演奏する傍ら、アレンジャーとして、1973年リリースの Ann Peebles の I CAN’T STAND THE RAIN Hi Records #165 や Al Green、さらにロッドのアトランティック・クロッシングでもサックス・プレイヤー&アレンジャーとして参加しています。Ray Harris から株を譲り受けて Hi Records の副社長にもなった Willie Mitchell の兄弟。息子の Jamal Mitchell が跡を継いでテナー・サックス奏者&アレンジャーとして活躍している)でございます。 このバッチリ作り込まれたサウンドは、その緻密さにおいてフツーのブルースのレヴェルをはるか超えたとこにあるよにも思えますが、でも逆にウソ臭くなる、っつーか「図式的」になってるよな気もいたします。なんだか、ブルースからもひとつ素材、探してこよ、てな具合で、あ、これマイナーだし、作り込み易いよ。なんてフンイキが想像されて、そこがかえってワタシなんかからすっと面白いんですが。 なんだか、バーのカウンターでオンナを口説いてるバックに流れてても違和感の無い「ゴージャスな(?)」音、って感じ。(注;ワタクシはここ 2,30年、バーなんて行ってないし、そんなトコでオンナを口説くシュミもございません・・・ ん?誰だ!シュミじゃなく「実力がない」んだろう?なんて言ってるのは!) James Milton Campbell Junior は、1934年 9月 7日(alt. 9 月17日)に、Mississippi 州の Inverness 郊外の小作人の家に生まれています。 はじめはラジオから流れて来る The Grand Ole Opry( Nashville の劇場で収録される C&W の番組)のような「白人の」音楽をよく耳にしていたようですが、徐々にミシシッピー・デルタに根ざしたゴスペルやブルースに染まっていったようです。彼の父は Big Milton といって、ローカルなブルース・ミュージシャンだったようで、その薫陶もあったコトでしょう。 12才の時、Little Milton(父の方の子供の中に、同じ James がいたので、それを知った彼は James を外した)は Greenville の有名な Nelson Street でデビューしました。10代の前半ですでに、デルタ周辺のローカル・クラブなどに出演し、表通り、裏通り、街角など、いろんな場所で演奏しています。 1953年、彼は18才のときに Ike Turner の紹介で Sam Phillips の Sun Records に吹き込み。デビュー・シングルは Beggin' My Baby ( B面は Somebody Told Me; Hi-194、Dec.1953 )でさらに二枚のシングル( If You Love Me / Alone And Blue; Hi-200 と Lookin' For My Baby / Homesick For My Baby; Hi-220 )を録音しています(ただし、初吹き込みとしては、その前に、ピアニストの Willie Love の伴奏で Jackson の Trumpet Records に1951年12月の V-8 Ford、さらに同じく Jackson の the Lebanon Club での演奏 Nelson Street Blues も存在しています)。しかし、これでブレークっちゅうワケには行かず、St.Louis の Bobbin Records での I'm A Lonely Man(と That Will Never Do も。1958 )が初のヒットと言えるかもしれません。 こう言うと語弊があるけど、それに目をつけた CHESS はミルトンを南部のブルース・サーキットから「全国区」に売れる!っちゅーことで(たぶん、ね)1960年に Checkers label との契約に持ち込んでいます。その「読み」は的中し、We're Gonna Make It が1965年に Billboard の R&B singles チャートの 1位を獲得しました。 1962年から、1971年までの間に(実際には1969年の Leonard Chess の死とともに CHESS は瓦解しはじめるのですが)Baby I Love You、If Walls Could Talk、Feel So Bad、Who's Cheating Who?、Grits Ain't Groceries などのヒットを連発しています。 1971年から1975年までの STAX 時代にはまた Walking The Back Streets や Cryin'、That's What Love Will Make You Do などのメガ・ヒットをトバしてます。また印象的な Little Bluebird(そ、この Waiting For に収録されてる大甘のナンバーざます)」もこの STAX でございますよん。しかしその STAX は1975年に破綻し、彼は Miami の TK/Glades Records に移ります。そこでは Friend of Mine がチャート・インしますがまたもやレーベルが傾いてしまう・・・ 1983年、MCA からアルバム Age Ain't Nothin But A Number をリリースし、タイトル・チューンはちょっとしたヒットになりますが、1984年には Malaco Records と契約し、それが彼の最も安定した契約関係となっております。 1988年には W. C. Handy Blues Entertainer of the Year Award を、2000年には「the Blues Hall of Fame」入り、Malaco からは14枚のアルバムがリリースされています。 でも、なんだか1980年代以降のリトル・ミルトンはココロに来ないんですよ。悪くはないんですがね・・・ Little Milton Campbell died about 8:50 a.m. of August 3, 2005. At Delta Medical Center in Memphis, Tenn. He was 70. Albert King、Freddie King、と来たので、今日はカナダの Richard Newell にして「オチ」にしよか?とも思いましたが、「基本的に」白人は採り上げないコトにしてますんでヤメました。 あ、でも日本人ならそのうち採り上げるかもしれません。 同じ「Colored」だし(って、白人に対する逆差別やねん)。 ニホンでブルースったら誰が真っ先に浮かぶかなあ? ま、ワタシの場合、世代的に、個人じゃなく、West Road Blues Band、Break Down に憂歌団、ってトコでしょか? で、自分がギター弾いてるもんだから、やはりフサノスケや内田勘太郎あたりが印象に残ってますねえ。 山岸あたり、スゴい!と良く言われますが、(で、実際に「スゴい」んでしょうが)印象に残ってるか?と言うとこの二人が「上」。 ま、だから、この二人がブルース・ギターでニホンのトップ!って言うんじゃなく、ワタシにとっての「プレゼンス」で言えば、でございます。 特にブレイク・ダウンの場合、津軽屋 B.B.の関係者によって主催された弘前ライヴで、至近距離からフサノスケ見てますからねえ。 ウェスト・ロードじゃあそんな経験が無いもんで、あまし印象に残ってないだけかも。 憂歌団は何年前だったか、バディ・ガイの雨の野音で竹田和夫(まだやってたの?と思った記憶アリ)なんかの後に出て来て、いっとき雨を忘れさしてくれました。 それにひところ関わっていた自主製作の映像作家たちとの付き合いの中で、憂歌団の音が全編に流れるモノクロームの作品があって、内容的にはなんのインパクトも無かったけど、そこに流れる勘太郎のスライドが、後のパリ・テキサスにおけるライ・クーダーのような(あるいは、もっと音の比重が大きいかも知れませんが)強烈なバック・グラウンドとして、映像にバイアスをかけていたのが深〜い刻印となってココロに残っていたせいもあってか、憂歌団にはハナからココロを開いて受け止めてたせいもあるのかもしれません。 |
permalink
No.501