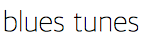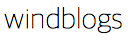Memories of You Willie Kent 2004-04-19 MON. | 今は亡き落語界の異才にしてワタクシがもっとも愛したライヴ・パフォーマー(あ、落語にそゆコトバ使っちゃいけないんだっけ?「高座映えがする」ってのかな?)、偉大なる桂 芝雀師匠がおっしゃっておられましたっけ。 ─ アホ声っちゅうのがおまして、もう聞いただけで、あ、こいつアホやな、と判る声っちゅうのがおます ─ で、まっこと不謹慎ながら、この Willie Kent はん、どーも、そのアホ声っちゅうヤツとちがうんかな?と思うのでございますが、後年の作品じゃもちっとシャキっとした歌も聴かせてくれるとはいえ、ど~もこの Delmark 40th Anniversary でのこの曲、芝雀師匠ふうに言えば「あまり賢そうやないで」。 いえいえ、曲はいいんですよ。ただ彼の声を聴いたとたん、トートツに芝雀師匠のセリフをなんでか思い出しちゃったもんで。 良くいえばおおらかな、ま、緊迫感が無い、とも言えますが、このユルユルなヴォーカルも案外いい味を出してます。 それにしても、このタイトルがまたいいですよね。とてもブルース・ナンバーのタイトルとは思えないじゃないの。Memories Of You・・・まるでハード・ボイルドのミステリーかなんかのタイトルみたいじゃん。 Willie Kent は 1936 年、Tennessee 州との州境から南に 100 マイルほどの Mississippi 州 Inverness で生まれています。KFFA の King Biscuit Time の放送を聴きまくり、Arthur Crudup、Sonny Boy Williamson、Robert Nighthawk に 11 才でのめりこみ、61 号線の Harlem Inn では Raymond Hill、Jackie Brenston、Howlin' Wolf、Clayton Love、Ike Turner、Little Milton などのライヴにも触れていたようです。 その彼が家を出たのが 13 才の時で、およそ 3 年間の空白(というのは彼を追いかける資料の上での、ね。本人にとっては「それなりのことがあった」 3 年間だったでしょうが)の後、1952 年、彼は Chicago に現れています。 彼は昼の仕事につき、夜は音楽に「捧げる」という生活を送りはじめたようで、仕事の同僚に Elmore James のいとこがいたこともあって、クラブからクラブへとブルースのライヴをめぐっていたようです。 そこで彼はマディやウルフはモチロン、J.B.Lenoir や Johnnie Jones、Eddie Taylor に A.C.Reed、J.B.Hutto なども知ったのでした。 おそらくその経験からでしょうが、彼はギターを買い込み、1959 年には親友の Willie Hudson を介して Ralph and the Red Tops というバンドに接近し、そのバンドの専属ドライヴァー兼マネージャー、さらに時にはシンガーとしても関わるようになります。 ところで、その Ralph and the Red Tops がとあるクラブに出演した際に、ベーシストが酔い潰れてて使いものにならない状態で現れ、しかもクラブからはすでに前金で貰ってしまっていたのでヤメるワケにもいかず、やむなく、彼が代理のベースとしてステージをこなしたのでした。 どうやらこれが彼の運命を決してしまったようで、それ以降の彼は、もっぱらベーシストとしての活動(あ、歌も続けてたみたいですが)に専念いたします。 1962 年には Little Walter のベースとして、また '60年 代中期にはマディやウルフのベースもこなし、Junior Parker ともやっていました。'60 年代晩期には Arthur Stallworth and the Chicago Playboys のベースとなり、時には Hip Linkchain、さらには「悪名高き(?)」 Jimmy Dawkins のバックも務めております。 特に Dawkins とは 1971 年のーロッパ・ツアーにも同行し、さらにアメリカに帰って来てからも Dawkins がホーム・グラウンドとしていた Ma Bea's Lounge のハウス・バンド Sugar Bear and the Beehives(ギターは Willie James Lyons、ドラム Robert Plunkett )に加わってバックで支えていたようで、そのハウス・バンドでは他にも Fenton Robinson、Hubert Sumlin、Eddie Clearwater、Jimmy Johnson、Carey Bell、Buster Benton、John Littlejohn、Mighty Joe Young といった錚々たるメンバーのバックを務めております。 1970 年代の晩期からは主に Eddie Taylor のバンドのベースとなり、1982 年からはレギュラー・メンバーとして正式に一員となりました。このバンドは Eddie Taylor の他に Johnny B. Moore のギター、Tim( Timothy: Eddie Taylor の長男)と Larry(同じく Eddie Taylor の次男。ちなみに三男が後に Eddie Taylor Junior と呼ばれるようになる Edward Taylor Jr.)のドラム、と Taylor 一家に Willie Kent が混じるカタチとなっています。 その Eddie Taylor が 1985 年の12月25日に死亡した後、彼は Willie Kent and the Gents をスタートさせ、自らベースを弾きながらヴォーカルをとる、というスタイルを始めています。ドラムには Tim Taylor、ギターに Jesse Williams と Johnny B. Moore で発足し、その後メンバーの異動はありましたが、基本的にウェスト・サイド・シカゴのサウンドをキープしている、と言っていいんじゃないでしょうか。King of Chicago's West Side Blues なんてアルバムもあるくらいで⋯ど〜こが!いやだ〜れがウエスト・サイドのブルース・キングやねん!ちゅうツッコミは飛び交いそうだけど。 ただしご本人は心臓の疾患が発見されて再三のバイパス手術も受けており、一時は活動も危ぶまれていたようですが、どうやら小康を保ち、昼の仕事からは足を洗って、音楽に専念しているようでしたが、2005年には結腸部にガンが見つかり、2006年 3 月 2 日には死亡しております。 この Willie Kent はん、アルバムだって十枚以上出してるし、現地シカゴじゃ「〜レコーディング・アーティスト」として、また数々の「賞」ももらってるちゅうことで「そこそこ」のプレゼンスがおありだったんでしょが、ニホンのブルースマニアで(青森に来るまでは)このヒトについてブルース界周辺で話題となったこと「絶無」だったような? なので青森のブルースフェスに来る、となってもウィリー・ケント?なにそれ?てな反応がほとんどでしたねえ。 まあ、このワタクシだってその仲間でして、青森に来たからこそ「賑やかし」に採り上げてはみたものの、あくまでも「ちょちょっ」と調べた付け焼き刃で、書いてるだけでございます。 青森のあと、このひとのアルバムを聴いてみよう、なんて気にはサラサラならなかった、ちゅうね⋯ |
permalink
No.725