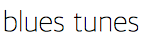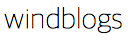| Standing in the Shadow of MOTOWN the Funk Bros. 2004-08-15 SUN. | 昨日に引き続き映像関係でございます( from Rickie the TFP)。 タムラ・モータウンなんて言葉を知る前から、たとえば the Supremes(もちろんダイアナ・ロスが加入してからの。その前のシュプリームスを知ってるひとってあまりいなかったんじゃないかなあ?と言っても、これはリアル・タイムでのハナシね)や the Temptationsなんかの音がワタクシの十代後半を彩るようになったのですが、それらの音を下支えしていたミュージシャンたちについては、殆ど興味を持ったことがありませんでした。 どうしても自分でも楽器を弾くようになると、やはり個性のある演奏をするプレイヤーに興味が偏り、あらゆる意味で記憶に残るよな存在ばかりに目が行ってしまいます。 しかし、ワタクシごときが言うまでもなく、たとえば日本にだって「レコーディング・ミュージシャン」というものが存在し、ワタクシなんぞ逆立ちしたって出来ないのですが、「楽譜」で詳細に指示されたディテールをミゴトに「その通り」弾きこなすんですねえ。 そのようなある種「無名」なミュージシャンが、実は日本でオン・エアされる音楽の大半を演奏してるワケです。例えば特に名を秘しますが某ロック・バンド(ま、正しくはロックっぽいポップスのバンド、なんでしょうが)など、そのようなスタジオ・ミュージシャンの演奏に振りマネしてるだけですし、も少し「弾ける」バンドでも、アドリブに至るまで、そんなフレーズ・メーカーのをコピーしてるだけ、ってのが多いんですよ。 スタジオ・ミュージシャンが兼ねる場合もありますが、むしろ、フレーズ・メーカーは、アドリブに強いプレイヤーが多く、そのひとが何通りも録った中からいいのをセレクトして、スタジオ・ミュージシャンがそれを完コピして「吹き込み」、主役のハズのバンド・メンバーはそれを必死でコピーする、っちゅう図式ですね。 コピーも出来ないし、自分のフレーズもペケっちゅうバンドのライヴじゃステージ・バックに控えたゴースト・プレイヤーが、ステージの映像をモニターで見ながら「実際に」演奏する、っちゅうことをします。もっとヒドいときにはカラオケなんて場合も! と、なにもそれが「けしからん!」なんて言ってるんじゃなく、ポップスじゃそんなの当たり前の世界でして、そこで「実際に」弾いている人たちって、滅多に表面に出てくることはありません。そして、そんな人たちが音楽産業を「かなり」支えてくれている、ってことを覚えておいてくださいませ。 もちろん、ワタクシなぞ、とても出来るよなレヴェルじゃございません。 譜面どおりに弾くことも出来なきゃ、いえ、それどころか、「いまのアドリブ良かったよ、も一回ちょっとトーン変えて弾いてみてくれる?」なんて言われても、え?いま、どんなの弾いたっけ?てなネがムセキニンなニンゲンでございますから、その道じゃあ、たちまちクビ!でございましょう。 ま、そのよーなスタジオ・ミュージシャンに「なること」、にはじぇんじぇんミリョクを感じないとも言えるんですが、それって「自分の不得意なものを悪く言う」っちゅう人間心理の為せるワザ、と言えないこともないですねえ。 Standing in the Shadow of MOTOWNというタイトルが示すように、あまたあるモータウンのヒット曲を陰で支えてきたミュージシャンたちの Now and Thenを丁寧に描いて行く中で、ライヴの映像が挿まれて行くのですが、やはりこれだけヒット曲も多いモータウンだけあって、ワタシだったら、あの曲は外せないなあ、っちゅう「我が心のモータウン・ナンバー」が殆ど含まれておらず(ま、版権その他の要素もあるのかもしれませんが)ちょっと寂しい思いもあります。 それでも、聴き覚えのある曲の連続で、それらがどのようなバッキングの上で成り立っていたのか、が垣間見えてとても面白いですね。 まず驚くのは各パートが厚いこと。 たとえばドラムだと、フル・セット二名の他にパーカッション、そしてタンバリン、という構成で、しかも、きちんとスコアを見ながら分担して完成度を上げています。 ギターだって三人(プラス、ワウワウ・ギターでは別な第四のギタリストがコーラス隊の横に立ってワウ・ペダルを使って弾いている!)もいるし、一人だけ、ってパートはベースのだけかも。 ともかく、すべてが緻密に計算された役割分担が出来上がっており、すべてスコアとして配られ、ミスが無い!スゴい仕事ですねえ。 一見、タンジュンに思えた各楽曲のバックにこれだけの人数がいるなんて! ただし、ワタシ個人の好みから言うと、これだけいるバックのミュージシャンの中で、うわっ、このひとスゴい!ってのが一人もいないんですね。 みんなそれぞれ、いい腕をしています。どのパートをとってもただもんじゃない。 でも、それはやはり「影」としての凄さであって、ああ、あんなふうになりたい、なんてゆう憧れの対象にはなりにくいんですよ。 むしろ、そのような「無色」の音をハイ・クォリティで供給できるからこそ、シンガーの個性と干渉することなく、楽曲を「活かす」ことが出来るんでしょうが。 さて、この映像についてですが、結局、オリジナルがチャートに登場してくるのをリアル・タイムで楽しんでいただけに、原曲に対する思い入れも強く、それだけに、その Funk Brothersをバックに当時のヒットを唄う(オリジナルじゃない)シンガーに対しては、どうしてもやや「辛く」見てしまいますね。 ブーツィ・コリンズが唄う Do You Love Meなんて、唄ヘタ過ぎ。色物としちゃ(?)プレゼンスはありますが、この曲じゃ、リズムが合ってないんですよ。 どうせだったら、もっとちゃんと音程もリズムも確かなひとに唄ってもらいたかったなあ。 あと、Joan某ってえ女性シンガーもしっくり来ませんでした。 そこ行くと、チャカ・カーンはスゴい!オリジナルがどうこう、なんて域を超えてます。 リッパなカヴァー・ヴァージョンとして、ひとつの独立した作品として完結してて、充分鑑賞に耐えます(ある意味、顔見てるだけでも飽きないしね)。 これまで、チャカ・カーンってさほどマジに聴いたことはなかったんですが、なんでか、一番モータウン的なものを感じさせてくれました。 芸術的過ぎず、かといって耳触りの良いメローなだけの音でもない、そこらが面白かったですねえ。 てなワケでフツーのミュージック・ヴィデオとはまったく違った、レーベルの音の作り方みたいなユニークな視点でとても楽しめる映像です。 個人的には、あのプレシジョン・ベースの音が(締まりが無いとこはちょっとワタクシの好みからはハズれますが)意外と重低音メインのセッティングで、ああ、こんなのもいいなあ、と思わせてくれました。そー言えば、しばらくプレシジョンから遠ざかってるなあ、なんてガラにもなく思ったりして。 ところで Five Guys Named Moe Inc.ってえ名前の会社が実在するなんて( North Hollywood, California)、なんだか嬉しくなりますねえ。 夕方ちかく BLUES'N に顔を出したら、N デパートで中古 CD のセールやってるって教えてくれました。 行ってみたらアナログ・ディスクの方が多いよな感じ(ブルースに関してはね)ですが、いまさらアナログってのもなあ。特に中古じゃ・・・ え?そんなことではリッパなコレクターにはなれないよ? あのねえ、ワタクシ、稀購盤を手に入れて、「やはりこれで聴くと彼の(あるいは彼女の)あまり知られていない部分が見えてきて云々」ちゅうよ〜な「持ってなきゃ判らんだろ、てな自慢」する輩がイッチバン嫌いなんですよ。そりゃ自慢したくなるキモチも判らないじゃないけど、そんなの「重箱の隅」じゃん。それをさも「これを聴かないまま彼の(あるいは彼女の)本質は語れない」などとぬかしくさる。 本質?そんなことより大事なんは「好きか嫌いか」だけじゃ! ありきたりの音源には本質が「無い」みたいな物言いはただの「不遜」。 |
permalink
No.846