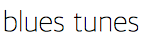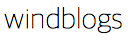| 22-20 Blues Skip James 2004-09-28 TUE. | すくなくともこの曲を聴く限りでは、昨日の日記で述べたような「極めて個性的な」ムードは窺えません。 これは(憶測に過ぎませんが)、こと彼のブルースに関して、ギターで歌うものと、ピアノで歌うもの、という二つの系列があり、しかも、その二つがまったく異なったルーツから彼の中に注ぎ込まれたから、ということなのではないでしょうか。 ポータブルな、その持ち歩く「嵩(かさ)」に対する「出せる音のヴォリューム&ヴァリエーション」というイミでのコスト・パフォーマンスならぬ、キャパシティ・パフォーマンスとでもいうべき(?)比がとっても良いギターという楽器と、たいていの場所で、喧噪の中でもダンス・ミュージックを「叩き出せる」、しかし、とても持って歩くなんてこと出来ないピアノって楽器、そのような本質的な部分から、ギターはあくまでプライヴェートを指向し、ピアノはパブリックな傾向を持つ、なんてことも言えそうですが、案外、そんなとこの「違い」がこのような異なった世界を作り上げているのかもしれません。 もちろん、楽器というものはなんでもそうでしょうが、「どの楽器でも大して違わない部分」と、それこそ「その楽器でなくては出来ないこと」を併せ持っています。 プライヴェート or パブリック、の違いは「楽器」によるものではなく、「弾き方」で決まるのだ、というのはモチロン正論にはちがいないのですが、各楽器そのものに付随した領域というものは決して「同じではありません」。 ひとりのソングライターがピアノで作った曲と、ギターで作った曲が「どう違う」のか? あいにくワタクシにはそのよーな経験が無いのでエラそーなことは言えないのですが、たぶん、同じではない、のではないか?っつー気がしますが、どーなんでしょね。 昨日の Devil Got My Woman と、今日の 22-20 Blues、伴奏楽器による偏向を受けているよな気がしませんか? ただ、彼の歌だけに意識を集中して聴いてみると、むしろ、このピアノの伴奏がそぐわないような感じも受けます。ホントはこんなふーな伴奏じゃないほーがいいんだけど、カラダが、指が、こんな伴奏をつけてしまうんだぁ、みたいな(?)「ま、いっか」的な割り切りを想像してしまうワタクシのココロが「穢れて」いるのかも⋯ このピアノは装飾音もふんだんにちりばめられた、やや「華やかな」傾向ですが、歌の持つテクスチュアとは「ちょっと」合ってないような気もしないではございません。 というワケで(?)、ま、彼のピアノによるブルースも採り上げときたかっただけでございます。機会がございましたら、是非、聴き比べてみてくださいませ。 さて、ここからは昨日「つづく」で中断したバイオの後半となります。 結局 Weona には 1923 年までいたようですが、なにやら、とある女を追って Memphis に出て、North Nichols Street にあった売春宿の専属ピアニストになったのでした。 しかし 1919 年から始まったアメリカの禁酒法(あ、禁酒法ってアメリカだけだと思ってるでしょ?実は Finland でも kieltolaki という名でそれが施行されておったのですねえ。ただ、アメリカより一年早い 1932 年に撤回されています。で、もっとも早くから施行していたのはカナダで、プリンス・エドワード島では 1900 からスタートし、もっとも遅かった Quebec はフィンランドやアメリカと同じ 1919 年から、となっています。しかも翌年には撤回され、そのためアンタッチャブルでお馴染みの Chicago に Michigan 湖を渡って「密輸」なんてハナシが出てくるワケです。一方のプリンス・エドワード島では終ったのももっとも遅く、1948 年!)が次第に売春業界(?)にも不況をもたらしたらしく、1924 年には売春宿を引き上げて Bentonia に帰ってきました。 以後、数年をそこで過ごすのですが、とりあえずは小作農になったものの、じきに「悪の道」に踏み込み、そこはやはりカエルの子はカエルっちゅうべきか、違法に製造されたり、密輸された酒類の密売で稼ぎ、女たちに宝石やら高価なドレスを買い与えてチヤホヤされていたようでございます。 ま、もっとも、そんなことばっかしてたワケじゃなく、例の Henry Stuckey とともに地元 Bentonia はもとより、Sidon に Jackson でも一緒に演奏し、練習し、ギターのウデを確実に上げていったのでした。 そうしてスリー・フィンガー・ピッキングをマスターした、とされていますが、それには Henry Stuckey のみならず、Charley Patton や Bo Carter にも影響を受けていたと思われます。 ただ、それによって完成された彼のスタイルを、E マイナー・オープン・チューニング(彼自身はそれを Cross-note tuning と呼んでいたとしていますが)とする資料と、一般の Vestapol、つまり通常の E オープンとしているものとに分かれています。 E マイナー・オープンだとすっと、Albert Collins みたいですねえ。 その独特の響きとファルセットのコンビネーションはやはり注目されたようで、Paramount Records のタレント・スカウト、H. C. Speir によって、Jackson の Farish Street 111 番地にあった Speir 自身のレコード・ショップでオーデションが行われ、その結果、Wisconsin 州 Grafton にあった Paramount のスタジオで 18 曲を録音(諸説あって、それを 17 曲である、とするもの、また 26 曲を録音したが、現在確認されているのは 18 曲だけである、としているもの・・・)した、と言われています。 そしてその中の一曲が今日の Devil Got My Woman だったのです。 その直後、父と再会したことがキッカケとなって、悪事から足を洗い、バプティスト教会の牧師となったらしく、父とともに Texas 州 Plano に赴き、1950 年代初頭に母が死んだことで Bentonia に戻って来ています(別な説では「大恐慌」によってレコードのセールスが止まり、充分なペイが行われなかったために、音楽を離れた、という見方も)。 しばらく聖職者としての生活を送っていたらしいのですが、1964 年にブルース・コレクターの John Fahey によって再発見され、Son House らとともに New Port Folk Festival に出演し、各地のカレッジでのライヴも行ったようです。 ただ、その束の間の栄光も長くは続かず、次第に彼の健康にはかげりが見え始め、1969 年10月 3 日には、ついにガンのために死亡しています。 Pennsylvania 州 Bala-Cynwyd の Mercon Cemetery に埋葬されたのでした。 |
permalink
No.889