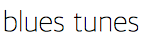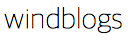| Need Your Lovin' Freddie Roulette 2004-11-08 MON. | Freddie Roulette の場合は、おそらく同じラップ・スタイル(ヒザの上で横向きに寝かせて弾くスタイルのことね)でも、デルタ系のスライドっちゅうよりは⋯ゼッタイに他ジャンルの、それこそハワイアンやらウエスターン・スウィングあたりの奏法に近いんじゃないか、と思わせるブっ飛びポルタメントがもたらす独特の「疾走感」ちゅうか「暴走感」はたまた「迷走感」が凄いんですよ! しかし、サザン・ロックのウェット・ウィリーの Leona のような疾走感とは異なり、向こうがレシプロのディーゼルから時折り黒煙を吐きながら爆走する 16 ホイーラーなら、Freddie Roulette はってえと、なにやら、その動力源すら定かではないフシギな物体がミョーな動きをしているが如きスリリングなそれで⋯ ま、むしろ「飛翔感(浮遊感?)」というほうが当たっているかもしれません。 リズム的には、先日の Junior Wells のナンバーに近いような気もしますが、なんたってこのブっ飛びスティール・ギター・ワークのおかげで仕上がりはとってもユニークで「スペイシー」な「なんだかよく判らんもの」になっております。 よく言いますよね、すべての楽器の中で(っちゅう中にはシンセサイザーは含めないでのハナシね)人間の肉声にもっとも近いのはサキソフォーンである、と。 ま、ワタクシもそれには別に異存はございません。 やはり「オーラル」なニュアンスってものが最もよく表現されてるなあ、っちゅう印象はございますからねえ。 ところが、この Freddie Roulette のギターときたら、そのソロの部分なんて、スッゴい「肉声的」なんですよ。 いきなりハイ・トーンにトんでくところ、高いピッチで素早く揺らすところ・・・まるで、どっかのおばはんが、カン高い声できゃあきゃあ言ってるみたいなデジャヴ(既視感)ならぬ「既聴感」を起こさせるに充分な「表情」があります。 なんだか、歌詞までも聞こえてきそうなその「おしゃべり」は、とっても饒舌で、なんだか次から次と、いっぱい話しかけてくるんですが、ナニ言ってるか判るのは Freddie クンだけらしく、自問自答みたく会話してるとこもあります。 これまでも Freddie Roulette は二曲を採り上げてますが、この曲では初めてベースが Willie Kent になってますねえ(前のは Vernon "Chico" Banks )。 いえいえ、それだけではありませ〜ん。残りのメンバーのうち二人も、今年夏の青森でのフェスティヴァルに一緒にきた Willie Kent & the Gents のメンバーなのですよ。 一人はポルタメントしまくりの Freddie クンにも惑わされることなく、シュアなピアノで背後を埋める Kenny Barker。 そして、独特な刻みで単調になりがちなリズムにいろんな表情を持たせているドラマーの Cleo Williams でございます。 彼らのおかげで 7 分を越える長さもさほど気にはなりません(ってのはワタシだけかも?)。 ワタクシにクソミソにけなされた、あの Frank Ash に似たコーラス・エフェクトがらみの「不純な(?)」音であらずもがな(キビシいのう)のギターを入れてるのは、前回の二曲ではベースを弾いてた Vernon "Chico" Banks。 う~ん、ま、中休み、ちょっとブレークてな役には立ってるのかなあ? それにしても、ここに残ってる音を作り上げたメンメンの 3/5 を青森の会場で実際にナマで見ていたんですねえ。 いわゆるデルタ系スライドってのとはまったくちゃう、歯が浮きそうな(?)うにょうにょスライドとして孤高の存在となってしまった(?)Freddie Roulette ですが、Bob Brozman はその著書、The History and Artistry of National Resonator Instruments の中で Oscar Woods は’20 年代の初頭に、米本土を巡業していたハワイアン・ショーを観た後でラップ・スタイル(ヒザの上に寝かせる弾き方)に変わった と書いているそうで(未確認)、どうやら、ハワイアン・スタイルのスライドがブルースにもたらした影響というものも無視することは出来ないようですね。 メロウで流れるようにスムースなハワイアン・スティール・ギターは’20 年代あるいは’30 年代にはもうすでにアメリカではメジャーな存在であって、Bob Brozman によればブルースばかりかジャズにも影響を与えている、とされています。 当然、Oscar Buddy Woods もその影響下にあり、それはそのまま Black Ace にも受け継がれていることでしょう。 このふたりは共にスパニッシュ・チューニング*のオープン G、あるいはオープン D での演奏をメインにしていましたが、テクでは Woods が上だったようです。 *スパニッシュ・チューニング・・・ E-A-E-A-C#-E( 6弦→1弦 )のオープン A、あるいはこの関係のまま全弦を1音下げるオープン G を指す。一方の Vestapol チューニングは、オープン D(D-A-D-F#-A-D)や、それを一音上げたオープン E(E-B-E-G#-B-E)がある。ただし、この Spanish と Vestapol の二つは「ベーシックな」オープン・チューニングに過ぎず、実際には、さらに多くのオープン・チューニングが存在します。 ハワイアン・スティールの 8 弦ギターあたりになると、全弦を同時に鳴らすことを「前提としない」チューニングがあり、3〜4 本をセットとしてマイナー系和音や maj.7th まで出せるチューニングも存在します。また、同様にレギュラー・チューニングではないものの、オープンで弾くと和音にならない「変則チューニング」も存在します。 例えば、1 弦あるいは 6 弦の E を 1 音下げて D にする、「セミ・オープン G 」と「ドロップ D 」、有名なアルバート・コリンズの「Em( E-B-E-G-B-E こちらは和音になるのでオープン・チューニングと言っても良いのですが、スライドではないので、全弦を同じフレットで弾くことはなさそ)チューニング」などもありますが、そちらは「スライド」を前提とはしていないので、ここではちょっとカンケー無いっすね。 っちゅう記述は Oscar Woods の Evil Hearted Woman Blues のとこでラップ・スタイルについて調べたときのものなんですが、Freddie Roulette の場合、そのスタイル以上にハワイアン・スライドの音の使い方、つうか音の振り回し方(?)を身につけてしまったのかもしれませんね。 そう、いい、とか、悪い、とかゆうことじゃなく、これを楽しめる、あるいは面白がれるかどうか、だけなんですよ。 けしからん!ちゅうかたも多いでしょうけど、これで笑い転げて楽しめたらそれもまたいい。みたいな(?) |
permalink
No.930