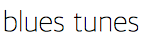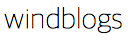| Off The Hook Earl Hooker 2004-06-01 TUE. | 6月に入って、なんだか梅雨っぽいお天気の日が増えてきそうな今日この頃、ひとつ爽やかなナンバーを、っつーワケでもないのですが、本日のブルースは、Gibson EDS-1275、つまりダブル・ネックの SG も勇ましい手練れギタリスト、 Earl Hooker さんでございますよん。 あ、とは申しましても、実際にこの曲でそのダブル・ネックを使ってるってワケじゃなさそうですが。ま、強いて言えば、曲の中ほどで、ほんの 4小節ほど、ん?オクターヴっぽい?ってとこがございまして、そこが 12弦のほーのネックだ!と言われれば、あっそう?てなもんですが、音からすっと、たぶんフツーのオクターヴ奏法だと思いますよ。 ややしっかりとかけたリヴァーブが快い、澄んだトーンは、途中でちょっとばかしハンバッキング臭さの強い音になったりもしますが、基本はフロント PU で拾った素直なノートを基本にしてるようで、あの Magic Sam に貸した Univox ほどのアクはございません。 ま、このアルバムが 1966年ですから、Univox U1885 が発売される前に録音されてるハズなんで、ここではちゃうギターを使っている・・・とすると、なんでわざわざダブル・ネック?っちゅうギモンは残るものの、この EDS-1275 を使ってたという可能性も無いワケではない・・・かな? それはともかく、実は先日、とあるところに、ライヴの音源を送るためにデュープ作業をしておったのですが、そのオープニングのナンバーが、(タイトルこそ違え)まさにこの Off The Hook そのものだなあ、と感心したついでに、あれ?ヒョっとして、ワシ、まだ一度も Earl Hooker 採り上げてないんちゃうか?と気付いたのでございます。 まあ、確かに、ブルースは「歌」じゃ!つー見地から行きますってえと、この Hooker クン、ちとヨワいとこがあるのは否めませんが、それでも、彼のギター・プレイがブルース界のみならず、Jimi Hendrix を始めとする蒼々たるギタリストのみなさまに与えたエイキョーを鑑みるに、ここは、いったん、そのよーなスジ論を離れ、「ブルースという音楽全体のレヴェル・アップ」に寄与した、ひとりの天才として・・・なんてゴタクを言う前に、よーは好きなんざんす。このギターが! でも、ギターの天才、っちゅうと想像されるよな「弾きまくり」や「ブっとびフレーズ」があるワケではおまへん。 ごくナチュラルな流れの中で「楽々と」メロディを発展させ、慈しむように弾いていきます。 いいなあ、こんなふうに力まずに弾けるようになりたい! Earl Zebedee Hooker(ミドル・ネームはどう発音すんでしょ?ゼベディ?)は 1929年、あるいは 1930年に Mississippi 州 Clarksdale で生まれた、とされています。フザケたことにアメリカのウィキペディアでは 1930 年、ニホンのウィキペディアでは 1929 年なんだよね。 生年ですらそんなですから、誕生日も判明していないのは仕方ないのかもしれません⋯と言いたいとこでしたが、どうやら 1/15 ちゅうことになったようでございます。ついでながら暮石に刻まれた生年は「 1929 」⋯ その彼が一才になるかならないかで一家は Chicago のサウス・サイドに移ったもののようですが、良く知られているように彼はジョン・リーの「いとこ」でもあります。 しかし、資料によっては彼をジョン・リーの First Cousin としているものと、Second Cousin としているものがあって、多少の混乱があります。 ま、どっちだっていいんですがね。 彼はブルースの真っ只中と言ってよいシカゴをその揺籃として育っていきます。 さらに両親ともに音楽を演奏した(ちょっと楽器までは判りませんでしたが)と言いますから、音楽的な環境としては、ワタクシなんぞにしてみりゃあヨダレがドド~っと出そうな「恵まれた」状態だったんじゃないでしょか。 ワタクシは、そのよーな環境がゼロに近いとっから過たず「ブルース」に着地することが出来たのはもはや奇跡と言っていいんじゃない?え?そんなことより Earl Hooker?はいはい、そーでしたね。 およそ 1945 年ころ、彼は Robert Nighthawk に会ったことで影響を受けたのか、ギターを始めることになったそうです。当時の Nighthawk は名義こそ Robert Lee McCoy ですが、すでにして Bluebird Recording Artist でした。 そのようにして、彼にギターとの関わりを与えてくれたのは Robert Nighthawk ですが(もちろん、奏法でも影響は受けています)、同時に彼はブルースのみならず、カントリー&ウエスターンやジャズ、そしてポピュラーからやがてはロックン・ロールにまで及ぶ広い範囲の中から様々なギター・プレイを吸収していったようです。 この時期のそのような視点が、彼のプレイに独特な彩りをあたえたのではないでしょうか? ま、なんだって、その道一本っちゅーのは、それはそれでリッパなことではあるのでございますが、元来、ニンゲンつーもの、けっしてそのよーにタンジュンな世界で充足する、とは思えませんから、その多様性のあり方みたいなとこに「個性」は存在する、とワタクシなんぞは愚考する次第でございます。 やがて彼はシカゴを出て南下し、Ike Turner のバンドに参加し、Sam Phillips の Sun Records に録音も経験しているようです。 1950年代の彼はどこか一社と長期契約を結ぶことなく、かなりな移動を繰り返していたようで、各地のクラブやジューク・ジョイントを回り、また数々のレコーディング・セッションに参加するためにフロリダからウエスト・コーストまでの各都市のスタジオを渡り歩きました。 その彼も 1960 年代の初頭には再びシカゴに戻り、一連の彼自身の代表作を Chess、Chief、さらに Age などのレーベルに残しています。 Blue Guitar、Tanya、Blues In D Natural(これって、同名の Red Lightnin' のアルバム・タイトルにもなってますよね)、Universal Rock なんて曲を生み出したのがこの時期です。 それらの自己名義のもの以外にも、たとえば Junior Wells の Chief 録音、さらにはマディや A. C. Reed、Ricky Allen、Lillian Offitt のバックでも活躍していますが、Lillian Offitt の Will My Man Be Home Tonight での印象的なギターは、以後、彼のトレードマークみたいなものになっていきました。 1971年、Otis Rush は、彼自身のアルバム、Right Place, Wrong Time の中でそのリフを導入したナンバー I Wonder Why を Earl Hooker に「捧げた」とされています。 また、この時期のマディとの仕事で、You Shook Me で実際にスライドを弾いているのは彼なのに、マディをスゴいスライド・ギタリスト、と思い込んだ層が実際にいた、としている資料もありました。 ケッキョク彼は「お馴染みの」 Day Job につくことなく、あくまでもプロ・ミュージシャンとして時代を疾走して行きます。 1960 年代後期には Arhoolie Records のオーナーである Chris Strachwitz が Buddy Guy の推薦で Earl Hooker に接触し、それ以降、この Two Bugs And A Roach( Arhoolie 1044、CD 324 )や The Moon Is Rising( Arhoolie CD 468 )などをリリースし、彼のギターはジャンルを超えてロック・ギタリストにまで愛される普遍性を獲得して行く(⋯なんてエラそうなこと言える立場じゃないんすけどね)ことに。 1969 年の晩秋、彼は Magic Sam などとも一緒に(だから Magic Sam が Earl Hooker のギターを使っているのねん) American Folk Blues Festival の一員としてヨーロッパ公演を行っていますが、その時すでに彼の結核はかなり進行していたものと思われます。 それから帰国した彼はすぐに、シカゴの結核療養施設に収容されたのですが、もはや容態はきわめて悪化しており、治療の甲斐もなく 1970 年 4 月21日に死亡しました。 彼の遺骸は Illinois 州 Cook County の Alsip にある Restvale Cemetery で眠っています。 |
permalink
No.768