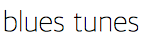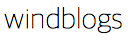| I Just Keep Loving Her Billy Branch 2004-05-17 MON. | 3 月15日付の日記、Othum Brown の Ora Nelle Blues のとこでも登場いたしましたが、HP 本篇のほーの Favorite Songs に収録されました barrelhouse bh-04 Chicago Boogie の I Just Keep Loving Her そのものを、Little Walter & Othum Brown という構成をそのまま Billy Branch & Kenny Neal という二人が採り上げたものでございます。 でございますから、出来ますれば、そちらのオリジナルの barrelhouse 版( P-Vine で CD 化されています。そのタイトルは シカゴ・ブルースの誕生 CHICAGO BOOGIE! 1947 PCD-1888 )の Little Walter & Othum Brown ヴァージョンも聴いていただけると、一層キョーミ深いものになるのでは、と愚考する次第でございます。 とは言っても、そんなの持ってないよう、って方もご心配なく、このニュー I Just Keep Loving Her、これだけを聴いていただいても充分に素晴らしい出来でございますよん。 およそハープとギターだけ、ってえ名演としちゃ、かの Big Walter Horton の Trouble In Mind( 2003-09-22 )ってのがありますが、あちらは Carey Bell も入ってハープを補強(?)し、ギターがこれまた名手 Eddie Taylor 大センセでございますからこりゃもう「別格」てなもんで、「さすが」と言うほかありません。 一方、この Billy Branch の唄う I Just Keep Loving Her、オリジナルのやや混沌とした熱っぽいエネルギーの替わりに、都会的なソリッド感(?)を手に入れ、さりとてスマートになり過ぎることなく、適度にフレンドリィな柔らかさをたたえています。 そしてそのハープですが、時には唄以上に歌っているように思うのでございますが、ハープ専門のみなさまはいかがお考えになりますか? ありきたりのフレーズに行かず、なんだかこの曲をとっても「楽しんでいる」みたいで、じっくりと慈しむが如く、ソロを組みたててるよな気がいたします。 バックにまわっている Kenny Neal も、ベーシックなリズム・パターンをモンクひとつ言わず(って録音の前か後にゃ言ってたかもしれんけど?)、あの Ora Nelle の世界をホーフツとさせるシンプルながらグルーヴィなサウンドをキープすることに徹し、Billy Branch を盛り立てております。う~んなかなかヤルなあ。 さて、Billy Branch と来れば、こりゃもう江戸川スリム!とーぜん Billy Branch Interview は欠かせません。 (あ、一方の Kenny Neal についちゃあ、昨年 10月 1日付の日記、Look But Don't Touch のほーでその Biography を書いてございますので、キョーミがおありの方はそちらをどーじょ) えどすりちゃまのことですから、あのサイトには書いていない数々のエピソードが「どっちゃり」あることでしょう。なんたって「直接の」交流から来てる情報ですからスゴいんですよ。 そんな彼の目の前で知ったふうに Billy Branchの Biography なんぞ書き出すってのはヘタすっとドトーのツッコミが?とキンチョーいたしますが、親交どころかまだお会いしたこととてないワタクシは、これまでに出ている様々な資料から「公式には」みたいなスタンスでアウト・ラインをなぞることといたしましょ。 William Earl Branch は Illinois 州の、Chicago からは Lake Michigan を右に見て 50km ほど北上したところにある町、Great Lakes の湖岸沿いに 137号線を北に辿った Waukegan 地区の Naval Hospital で 1951年10月 3日に、最終的には 4人となる一家の子供たちの一番最初の子として生まれています。 しかし、彼がまだ 4才の時に一家は Los Angeles に移ったようで、そこで育ったと言ってもよいのではないでしょうか。 Naval Hospital =つまり海軍病院ですね。そこで生まれた、とゆーことは、父が海軍の軍属だったのでしょうか?もしそうなら、その後の西海岸への移転も、そちらの基地に転属された結果なのかもしれません。 南部や中西部あたりからウエスト・コーストへ、という移動は「ありがち」ですが、通常、シカゴ( Great Lakes は実質上、シカゴの文化・商業圏内にあります)から「わざわざ」西海岸へ、という流れは考え難いですからねえ。 とは言え、それについて言及している資料には出会っておりませんので、これはあくまでも推論の域を出ませんが。 その彼が最初にハープを持ったのは 10才である、としている資料もありましたが、1997年の Steven Sharp によるインタビューでは 11才の時だ、と語っています。 そして Los で初めて聴いたブルースについては Wolfman Jack(本名 Robert Weston Smith、1939,1,21-1995,7,1。1958年から 1966年にかけて Texas 州 Del Rio から国境を越えたスグ、Mexico は Coahuila 州 の Ciudad Acuña にあった送信出力 250KW という AM ステーション XERF で D.J.を勤め、西部諸州から条件次第ではアメリカ国内の大半のリスナーに音楽を届けた伝説的な人物。映画アメリカン・グラフィティにも出演)の放送あたりからではないか、と答えていますが、さほど強烈な印象ではなかったようです。当時、家族もブルースを特に聴取する習慣も無かったらしく(もっとも、後で判ったらしいのですが、彼の母はシカゴで生まれ育っただけあって、若いころにはブルースがかなり好きだったそうです)、ケッキョク彼の Los Angeles 時代は、ブルースとはあまり縁の無い生活だったようです。 その彼が 17才の時に Chicago に来て、とは言ってもほとんど「ブルース」というものの知識も無かったらしいのですが、高校の上級生になったとき、ちょっとした研究発表をすることとなり、そこで「革命」というテーマに沿ってジミ・ヘンドリックスなどを採り上げ、それはクラスではおおいにウケたらしいのですが、それを監修する立場の教師からは、「ブルース」についての言及がありましたが、その頃の彼はまだブルースに意識のピントを合わせてはいなかったようです。 当時の彼の音楽との関わりですが、まずは祖母が買ってくれたオルガンや父の Magnus Chord Organ( 25鍵で、どうやら基本的には Cheap な Plastic 製の Toy Instrumentで、Worth about 15$、つまりイマで換算すると 2000円くらいで買えるオモチャのオルガンってことになりますか?画像は http://www.combo-organ.com/whatisit.htm で。Vox Jaguar などの、This is a combo organ に対比して、This is not 側の筆頭にシンセなどを従えて登場してるのが笑えます)などで Knock On Wood や I'll Be There を弾いて遊んでおり、さらにピアノのある知人のところではそれも弾きまくっていた、と言いますから、音楽的な下地は充分にあった、と言えるのではないでしょうか。 そして、それはハープにも活かされている、と思うのですがいかがっしょ? この I Just Keep Loving Her でのソロを聴いていますと、ハープには素人のワタクシの耳には「経過音」など、それまでの通常のブルース・ハープではあまり使わない音が時折り紛れ込んでいるように感じられるのですが、そのヘンはえどすりちゃまから後ほど御教唆いただけるやもしれません。 ところで、シカゴでは父とその後妻と思われる「継母」と一緒に暮らし始めた、といいますから、そこらイロイロと事情があったんでしょうなあ。 その彼が 1969年の Grant Park のフェスティヴァルに出会い、(当時はブルースについて詳しくはなかったため、記憶は多少あやふやらしいのですが) Junior Wells やマディ、さらに Big Mama Thornton に Koko Taylor などの音楽に触れ、Chicago Circle キャンパスの建築を専攻していた孤独でやや鬱屈していた生活に落ち込みかけていた彼の心に響いてくるものを感じ、家に帰って、当時フィルム現像(&同時プリントか?)の景品として貰ってたジョン・メイオールのアルバムを引っ張り出し、それに合わせてハープを吹くようになった、と答えています。 もっともその頃にはハープを曲のキーに応じて替える、ということを知らずに苦労したらしいのですが。 そんな彼がやがてサウスサイド(の 35番街と King ストリートのとこ、と「言ってる」と思うんだけど、現地を知らないので推測でげす)で Rahsaan という男に出会い、彼のハープは「ブルースではない」と告げられ(!・・・やっぱりねえ。メイオールじゃあ)、Sonny Boy や Little Walter の存在を教えられることになったようで(酒を呑むことも教えられたみたいですが)、これが大きな転機だったのかもしれません。 やがて彼は Five Stages というとこに連れて行かれ、そこでマディを見たようですが(なにやら Otis Spann の追悼のような催しだったらしい)、そこでは目の前で Rahsaan がハープを持ってステージに乱入(?)するさまを見て、ハーピストはあらゆる機会を逃さないようにしなきゃイカンのだな、と学んだみたい(ってえとこが、ちとスラング混じりの会話文なもんで、ちとその内容には自信がおまへん。WEB 翻訳じゃワケ判らんタワゴトにされちゃうし・・・)。 やがて彼は Junior Wells の義理の息子だった Lucius Barner と知りあいます。そしてその Lucius が彼を Theresa's に連れていってくれて、Junior Wells は二人を見て「入ってよし」と言ってくれたそうです。 またその後、彼がよく聴きに行ったのが Short Stuff(ハープの Jim Liban と、キーボードの Junior Brantley からなる Wisconsin のバンド。あまり詳しくはないのですが、1970年代から 1980年代に活躍してたらしい、白人のブルース系ロックのバンド?)で、彼らの出てたノースサイドのクラブ Alice's Revisited では Carey Bell、Charlie Musselwhite にも触れています。 Short Stuff の Jim Liban は、彼をステージに招き上げてくれた最初のプレイヤー(正確には「のひとり」)で、他にも Lefty Dizz、Junior Wells、Buddy Scott などが彼のブルースへのスタートをサポートしてくれたそうです。 やがて彼の通っていた学校でライヴがあったりすると、仲間の学生たちが「Billy をステージに!」と騒いでくれるようになり、その仲間たちはまたクラブにも来てくれるようになっていきました。 そんな時、ハープ・プレイヤーの Little Mack が WVON に出てたときに「俺は世界一のハーピストさ。ハープで俺に勝とう、ってえヤツはいるかい?誰の挑戦でも受けるぜ」と言ったのを受けて実際に挑戦し、Little Mack は負けを認めなかったものの、居合せた Jim O'Neal や Bruce Iglauer には確実にその存在を認められることになったのです。 そのころの彼はどうかすると、学校にも行かず朝っぱらから楽器が出来るとなれば(たとえそれがチューバやフルートであろうと)自宅でジャム・セッションを繰り広げていたそうで、家族にとっちゃエラい迷惑だったでしょうね。 そして学校で知りあった Sarah という秘書が Willie Dixon の秘書業務を行っていると知った彼は、その電話番号を手に入れ、自分を売り込んで、会う約束をとりつけています。 ちょうどハンク・アーロンがベイブ・ルースの本塁打数を抜いたことを記念したナンバーを吹き込むリハに行った彼はさっそくハープを吹き、Chess のスタジオに明日、来るように、と言われたのでした。 その時のメンツは Lafayette Leake、Buster Benton、Clifton James そして Willie Dixon で、Carey Bell が不在だったらしいんですね。あ、ヴォーカルは McKinley Mitchell。 Billy Branch ついに初レコーディングの一幕、ここから先はまたいつの日にか、ということで丁度お時間もよろしいようで・・・ |
permalink
No.753